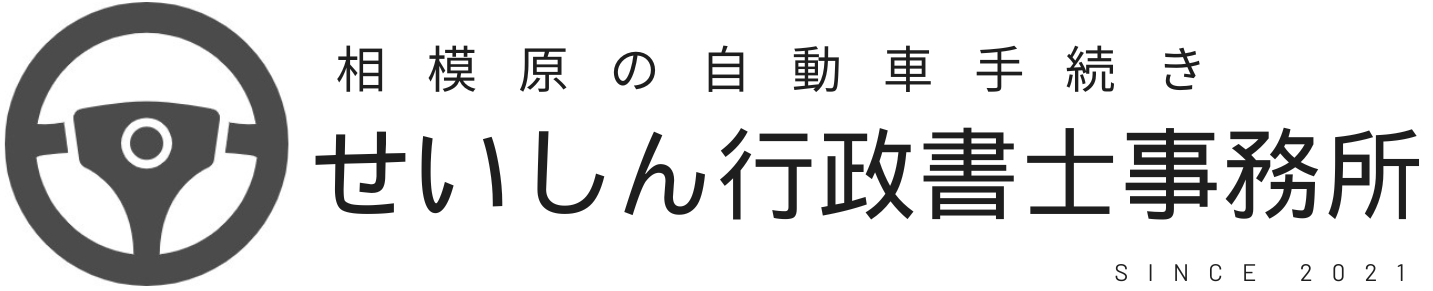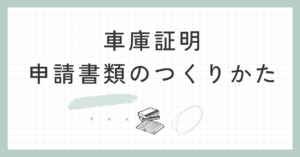レンタカー事業の許認可申請の方法
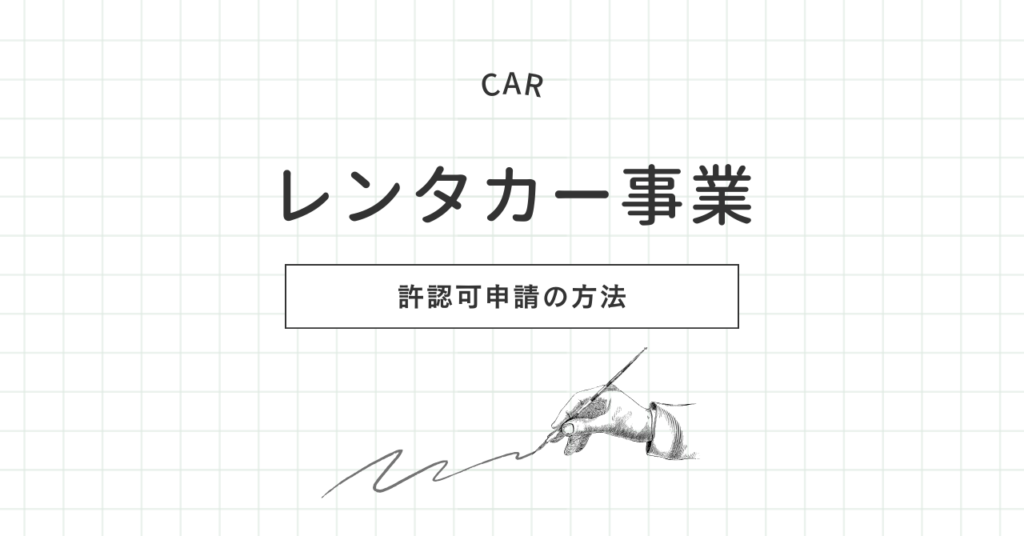
レンタカー(自家用自動車有償貸渡)事業を始めるには、その事業をする場所の管轄となる運輸局に許可を得る必要があります。
道路運送法
(有償貸渡し)
第80条1項
自家用自動車は、国土交通大臣の許可を受けなければ、業として有償で貸し渡してはならない。ただし、その借受人が当該自家用自動車の使用者である場合は、この限りでない。
2項
国土交通大臣は、自家用自動車の貸渡しの態様が自動車運送事業の経営に類似していると認める場合を除くほか、前項の許可をしなければならない。
無許可でレンタカー業をおこなうと、100万円以下の罰金、当該自動車の使用禁止処分等を受けることになりますのでかならず許可をとってから事業をおこないましょう。
Table of Contents
申請の前に
申請は法人でも個人でも可能です。その場合、添付書類に違いがありますので注意しましょう。
法人が許可申請する場合
提出する書類のなかに、法人の登記簿謄本を添付する必要があります。その登記簿謄本の事業目的のなかに、レンタカー事業の項目が加えられている必要があります。申請の前に登記にあらかじめ項目を加えておきましょう。
事前に必ず確認してください
欠格事由
レンタカー事業の許可申請者が欠格事由に該当する場合は、許可がおりませんので注意が必要です。以下、申請者が欠格となる内容をまとめました。
□1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者
関東運輸局神奈川運輸支局
□各種自動車運送事業許可の取消しを受け、取消しの日から2年経過していない者
□各種自動車運送事業許可の取消しの処分の通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定するまでの間に、事業又は貸渡の廃止の届出をした者(相当の理由がある者を除く)で、当該届出の日から2年を経過していない者
□各種自動車運送事業の監査が行われた日から許可の取消し処分にかかる聴聞決定予定日までの間に、事業又は貸渡しの廃止の届出をした者(相当の理由がある者を除く)で、当該届出の日から2年を経過していない者
□未成年者の場合、その法定代理人が上記のいずれかに該当する者
□申請者が法人の場合でその法人の役員が上記のいずれかに該当するとき
□申請者及びその役員が申請日前2年前以降に自動車運送事業経営類似行為によって処分を受けているとき
レンタカーにできる車両
□自家用乗用車
関東運輸局神奈川運輸支局
□自家用マイクロバス(乗車定員11人以上29人以下、かつ、車両の長さが7m以下)
□自家用トラック
□特種用途自動車
□二輪車
保険の加入義務
貸渡自動車は、事故を起こした場合に備えて、十分な補償を行いうるように次に定める自動車保険に最低限加入する必要があります。
・対人保険 1人当たり8,000万円以上
関東運輸局神奈川運輸支局
・対人保険 1件当たり200万円以上
・搭乗者保険 搭乗者1人当たり500万円以上(搭乗者が補償対象となる人身傷害保険も含む)
なお、対人・対物保険は無制限の保険に加入することをお勧めしています。一般的な保険会社であるかネットの保険会社であるかは特に問われません。きちんと保険に加入し、保険料を支払っていることが必要です。
中古車を利用する場合は古物商許可が必要
中古車をレンタカーにする場合、古物許可を受けている必要があります。なお、古物商の取得はレンタカー業の許可申請よりも時間がかかります(1〜2ヶ月程度の審査期間)ので、前もって許可を受けておく必要があります。
整備管理者
営業所の保有車両の数が10台以上になると、「整備管理者」の選任と届出、及び「整備管理規程」の制定が必要になります。1つの営業所に以下の車両の各台数がある場合は、整備管理者を選任する必要があります。
整備管理者とは、一定数以上の車両を事業に使用する際に必要な、自動車の点検・整備及び自動車車庫の管理に関する事項を処理する者のことをいいます。この場合の整備管理者は、「実務経験を持ち、研修を受けた者」又は「自動車整備士の資格を持っている者」がなることができます。逆に言えば、小規模の台数で事業をスタートする場合など、一定数以下の車両の保有であれば必要ありません。
そして、一定以上の車両数とは、以下のとおりです。
・バス(乗車定員が11人以上の車両)→1台以上
関東運輸局神奈川運輸支局
・大型トラック(車両総重量8トン以上)→5台以上
・その他の車両→10台以上
たとえば、「その他の車両」が10台というのは、あくまで1つの営業所で保有する車両数が10台という意味です。複数の営業所を運営する場合に、すべての営業所が保有する車両の数を合計して10台ということではありません。そして、車両数が上記を満たした場合は、1営業所ごとに整備管理者を置く必要があります。
禁止行為
許可を得て、営業を行うにあたって以下の行為は禁止されます。
・利用顧客の個人情報を他者に提供すること(約款に個人情報の定めのある場合を除く)
・自動車の貸渡し以外に運転者の紹介やあっせんをすること
・自動車の貸渡しのため、自分の名義を他人に利用させること
手続きの流れ
1 申請書類、添付書類を窓口に提出
2 審査期間に1ヶ月程度
3 許可証の交付、登録免許税 90,000円納付ののち営業が可能になります
4 車両の登録(わ・れナンバーでの登録)、車庫証明など自動車登録手続き
5 実際の営業開始
必要な書類
申請書類 (←DLできます)
□自家用自動車有償貸渡許可申請書
□宣誓書
□事務所別車種別配置車両数一覧表
□貸渡しの実施計画
添付書類
□法人の場合は法人登記簿謄本、個人の場合は住民票
□料金表
□貸渡約款
添付書類について
料金表
自動車の車種や年式、グレードなどを記載のうえ、利用料金を掲載します。
・6時間まで
・12時間まで
・24時間まで
・1日
・超過料金(1時間ごと)
といったかたちで基本的な料金の設定をします。また、オプション料金、各種手数料、補償金などを定めて明記します。
貸渡約款
貸渡をする契約のルールをあらかじめ公表し、責任の所在を明らかにする目的で作成・提出する必要がある大事な書類です。以下の項目について定めながら、ご自身が盛り込みたいとお考えの項目を追加していくことになります。
・予約について
・貸渡しについて
・使用について
・返還について
・故障、事故、盗難時の対応について
・賠償、補償について
・契約の解除について
・個人情報の取り扱いについて
・雑則(消費税、遅延損害金、インボイスなど)
ご相談ください
申請に必要な書類の準備については、この料金表と約款の作成に時間がかかります。ご自身で作成される場合は他社の約款を参考にしつつ、適宜加筆修正と削除をすることとなります。もし、レンタカー事業の許可申請を検討されている場合はぜひ弊所にご相談ください。