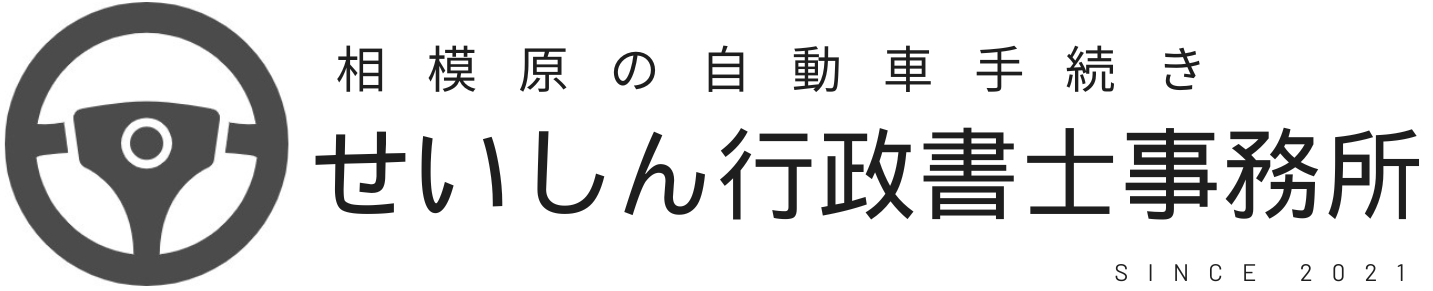行政手続きについて考える

各種許可申請のご相談をお受けするなかで、許認可申請の手続きそのものではなくて「審査基準」を読みながら、以前に比べてより『受験生の頃に疑問だったことや理解しきれていなかったこと』を考えるようになりました。
よく「行政書士の試験は実務に直結しない」と聞きます。実際、試験を受けるということのみであればそれも合っているなとも感じます。一方で、実務をおこなっていると『これはもっと深く学習しておくべきだったかもしれない』と感じることも少なくありません。
私たち行政書士は紛争には手出しできません(もちろん特定を取っておられる先生方は不服申し立てができます)。ですから、許認可申請をおこなうにあたってはきちんとルールに沿って審査を通すことが大切になります。
登録前後、「業務をおこなうには役所の窓口で使っている本と同じものを手に入れた方が良い」と聞いたことがあります。仕事を始めてからの不安な時期、私もそれがいいのかなと考えることもありました。
しかし、ある先生の許認可申請のお話を聞いた時に『この先生は許認可申請の’マニュアル’みたいなものには頼っていないのかもしれない』と感じることがありました。広い知識と深い思考で困難事例の許認可を通していたのです。実際にお話をうかがうと、本当によく学んで実務をされているということを思い知らされ、自分にはここまで達することができるのだろうかと不安になったものです。
その経験から、まずは基礎をしっかり身につけるべきだと感じました。もっとも、資格用のテキストは広く浅く書かれたものが多いです。今一度、勉強をしなおそうと考えて電子書籍でいくつか法律の本を購入しました。現在、読んでいるのは日本評論社の『行政法』です。

この本のいいところは、手続きの流れと個別法がどの部分でどう使われているのかが導入部分で説明されているところだと私は感じています。具体性があり、判例の引用もすっきりしていてわかりやすいです。全体のイメージをつかみやすく、この本をベースに広げていくのもいいのではないでしょうか。
今はいろんな本があっていいなぁと思います。自分が受験生だったときよりも便利で豊富です。電子書籍なら持ち運びも便利で、ものも減らせます。日経評論社の日評ベーシック・シリーズはわりと好きで、他にも憲法や民事訴訟法なんかも購入しています。
自動車の手続きが多いので、あまり許認可申請のことを深堀してこなかったなぁと反省するとともに、今後はしっかりと勉強して依頼者さまのお役に立てるような行政書士になる所存です。